仮想通貨投資が一般的になった現在、「親が仮想通貨を保有していたが、相続税はどうなるのか」「仮想通貨の評価額はどのように算定すればいいのか」といった相談が税理士事務所にも増えています。
デジタル資産である仮想通貨の相続は、従来の株式や不動産とは異なる特殊性があり、多くの方が戸惑われるのも無理はありません。価格が24時間365日変動し、複数の取引所で異なる価格がついている仮想通貨を、どの時点でどのように評価すべきか、国税庁のルールを正確に理解している方は少ないのが現状です。
しかし、仮想通貨も立派な相続財産であり、適正な申告を怠れば税務調査や追徴課税のリスクもあります。一方で、正しい知識さえあれば、適切な評価と申告により安心して相続手続きを進めることができます。
この記事では、国税庁の公式見解に基づき、仮想通貨の相続税について評価方法から申告手続きまで詳しく解説します。相続が発生した方はもちろん、将来的な相続対策を考えている方にも役立つ内容となっています。
なお、仮想通貨投資を始める際は、金融庁登録済みの信頼できる取引所を選ぶことが重要です。コインチェックなら初心者でも安心して取引を始められ、相続時に必要な取引履歴の管理機能も充実しています。まずは口座開設から始めてみましょう。
\ 取扱通貨数が国内最大クラス /
目次
仮想通貨の相続税とは?国税庁の基本的な考え方
仮想通貨も相続財産として課税対象
国税庁は、仮想通貨を「財産的価値を有する」ものとして明確に位置づけており、相続や贈与の際には課税対象となることを公表しています。これは、仮想通貨が物理的な形を持たないデジタル資産であっても、経済的価値があることに変わりはないためです。
具体的には以下の取り扱いとなります:
- ビットコイン、イーサリアムなどの主要仮想通貨:すべて相続財産として評価対象
- アルトコインやマイナー通貨:取引実績があるものは課税対象
- ステーキング報酬やマイニング報酬:相続開始時点で確定している分は財産評価に含む
- NFT(Non-Fungible Token):価値が明確なものは評価対象
相続税法では、相続や遺贈により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となると定められています。仮想通貨もこの原則の例外ではなく、相続開始時点での時価で評価し、他の相続財産と合算して相続税を計算することになります。
国税庁が示す仮想通貨の定義と範囲
国税庁は、仮想通貨について「資金決済に関する法律第2条第5項に規定する暗号資産」として定義しています。この定義に基づき、以下のような特徴を持つデジタル資産が相続税の対象となります:
- 代価の弁済のために不特定の者に対して使用可能
- 不特定の者を相手方として売買可能
- 電子情報処理組織を用いて移転可能
- 法定通貨建ての資産でない
ただし、すべてのデジタル資産が対象となるわけではありません。国税庁では、以下のような基準で判断しています:
課税対象となるもの:
- 仮想通貨取引所で取引されている主要通貨
- DeFiプロトコルで保有するトークン
- 価値が明確に判定できるNFT
- 企業が発行する独自トークン(価値評価可能なもの)
課税対象外となる可能性があるもの:
- 価値がゼロまたは評価困難な通貨
- 技術的に移転不可能なトークン
- ゲーム内通貨(現実価値への交換不可能なもの)
仮想通貨の相続税評価方法|国税庁公式見解
相続開始時点での評価額算定ルール
国税庁では、仮想通貨の相続税評価について「相続開始の時における時価」によることを明確に示しています。この「時価」の算定方法について、具体的なルールが定められています。
基本的な評価時点:
- 相続開始日:被相続人が死亡した日の午後11時59分時点
- 評価単位:保有する仮想通貨の種類別に評価
- 価格の確認:複数の取引所価格を参照して合理的に算定
重要なポイントは、仮想通貨が24時間取引されているため、相続開始時点を正確に特定する必要があることです。株式市場のように取引時間が限定されていないため、死亡時刻に最も近い時点での価格を採用します。
取引所の価格を基準とした評価方法
国税庁は、仮想通貨の時価算定について以下の優先順位を示しています:
1. 活発な市場における公表価格
- 仮想通貨取引所での取引価格
- 出来高が十分にある取引所の価格を優先
- 日本国内の金融庁登録業者の価格を重視
2. 活発でない市場における価格
- 取引量が少ない取引所の価格
- 海外取引所の価格(国内取引所での取扱いがない場合)
3. その他の合理的な価格算定方法
- 類似する仮想通貨の価格を基準とした評価
- 第三者評価機関による価格データ
具体的な算定手順は以下のとおりです:
- 主要取引所での価格確認
- コインチェック、bitFlyer、GMOコインなどの価格をチェック
- 相続開始時点に最も近い取引価格を採用
- 価格の妥当性検証
- 異常な価格変動がないか確認
- 複数取引所での価格乖離が大きい場合は平均値を採用
- 評価額の算定
- 保有数量 × 単価 = 相続税評価額
- 小数点以下の端数処理は一般的な商慣習に従う
複数取引所がある場合の評価基準
同一の仮想通貨が複数の取引所で異なる価格で取引されている場合、どの価格を採用すべきかは重要な論点です。国税庁では以下の考え方を示しています:
価格採用の優先順位:
- 最も取引量の多い取引所の価格
- 1日の出来高が最大の取引所
- 流動性が高く、価格の信頼性が高い市場
- 被相続人が主に利用していた取引所の価格
- 実際の取引実績がある取引所
- 売却の可能性が高い市場での価格
- 複数取引所の平均価格
- 価格差が大きい場合の調整方法
- 異常値を除外した平均価格の算定
実務上の注意点:
- 国内取引所を海外取引所より優先
- 金融庁未登録業者の価格は参考程度に留める
- 価格操作の疑いがある異常な価格は除外
- 取引停止中の取引所の価格は採用しない
仮想通貨相続税の申告手続きと必要書類
相続税申告の期限と提出先
仮想通貨を含む相続財産がある場合の申告期限と手続きについて説明します。
申告期限:
- 相続開始を知った日の翌日から10か月以内
- 期限が土日祝日の場合は翌営業日まで
- 期限内申告により配偶者控除等の特例適用可能
申告義務の判定: 相続税の申告が必要となるのは、以下の条件を満たす場合です:
- 相続財産の合計額が基礎控除額を超える場合
- 基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
- 仮想通貨も相続財産の合計に含む
- 税額控除等の特例を受ける場合
- 配偶者控除、小規模宅地等の特例など
- 税額がゼロになる場合でも申告が必要
提出先:
- 被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署
- 相続人の住所地ではないことに注意
- e-Taxでの電子申告も可能
準備すべき書類一覧
仮想通貨の相続税申告に必要な書類は以下のとおりです:
基本書類:
- 相続税申告書(第1表から第15表)
- 被相続人の戸籍謄本(死亡から出生まで)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
仮想通貨関連の特別書類:
- 取引所残高証明書
- 相続開始日時点での保有数量
- 各取引所から発行を受ける
- 複数取引所利用の場合はすべて必要
- 価格算定根拠資料
- 相続開始日時点の価格データ
- 取引所のスクリーンショットまたは公式データ
- 価格算定方法の説明書
- ウォレット残高証明
- ハードウェアウォレットの残高
- ブロックチェーンエクスプローラーの記録
- 秘密鍵またはシードフレーズの管理状況
- 取引履歴
- 過去1年間の売買履歴
- 取得価額の算定資料
- ステーキング報酬等の収入記録
その他の関連書類:
- 遺産分割協議書(分割が完了している場合)
- 相続放棄申述書(相続放棄者がいる場合)
- 仮想通貨評価に関する税理士意見書(複雑な場合)
申告書への記載方法と注意点
仮想通貨の相続税申告書への記載方法について、実務上のポイントを説明します。
記載場所と方法:
- 第11表(相続税がかかる財産の明細書)
- 「その他の財産」欄に記載
- 財産の種類:「仮想通貨(●●コイン)」
- 財産の所在:「○○取引所」
- 数量:保有コイン数
- 単価:相続開始日時点の価格
- 評価額:数量×単価
- 記載例:
財産の種類:仮想通貨(ビットコイン)
所在場所:コインチェック
数量:1.5BTC
単価:4,500,000円
評価額:6,750,000円
記載上の注意点:
- 通貨別に分けて記載:ビットコイン、イーサリアムなど通貨ごとに行を分ける
- 取引所別の管理:同一通貨でも取引所が異なる場合は分けて記載
- 小数点の処理:保有数量は小数点以下8桁まで正確に記載
- 価格の根拠明示:評価価格の算定根拠を別紙で説明
- 外貨建て処理:海外取引所の場合は円換算レートも記載
仮想通貨相続でよくある間違いと注意点
申告漏れが発生しやすいケース
仮想通貨の相続税申告において、実務上よく見受けられる申告漏れのパターンについて解説します。
1. 複数取引所・ウォレットの見落とし
最も多い申告漏れのケースは、被相続人が複数の取引所や個人ウォレットに分散して仮想通貨を保有していた場合の見落としです。
よくある見落としパターン:
- 国内取引所のアカウント情報は把握していても、海外取引所を見落とし
- メインで使用していた取引所は申告したが、少額の別取引所を失念
- 取引所だけでなく、個人ウォレット(MetaMaskなど)の残高を確認していない
- DeFiプロトコルでのステーキング残高の申告漏れ
対策方法:
- 被相続人のメールボックスを確認し、取引所からの通知メールをチェック
- スマートフォン・パソコンのアプリ一覧から仮想通貨関連アプリを確認
- 銀行口座の入出金履歴から仮想通貨取引所への送金記録を調査
- 家族への聞き取りや書類整理で見つかった情報を総合的に判断
2. 評価時点の誤り
仮想通貨は24時間取引されているため、評価時点を間違えるケースが散見されます。
典型的な間違い:
- 死亡日の始値(0:00時点)で評価してしまう
- 翌日の価格を使用してしまう
- 日本時間と現地時間の混同
- 週末や祝日の価格取得方法の誤解
正しい評価方法:
- 相続開始日時(死亡時刻)に最も近い取引価格を採用
- 土日祝日でも取引は継続されているため、該当時点の価格を確認
- 取引所のAPIデータやチャートで正確な時刻の価格を確認
- 複数の価格情報源を確認して妥当性をチェック
3. 取得コストとの混同
相続税評価額と所得税計算での取得費を混同するケースも多く見られます。
混同しやすいポイント:
- 相続税では相続開始時の時価で評価(取得価額は無関係)
- 相続人が売却する際は相続税評価額が取得費となる
- 被相続人の購入価額は相続税計算には影響しない
評価額算定での典型的なミス
1. 価格データの信頼性不足
信頼性の低いデータソースを使用することで生じる問題:
- 個人サイトやアプリの価格情報を使用
- 取引量が極端に少ない取引所の価格を採用
- 価格操作の疑いがある異常な価格での評価
- 取引停止中の取引所データの使用
適切な価格情報源:
- 金融庁登録済み暗号資産交換業者の価格
- 出来高の多い主要取引所の価格
- 複数の信頼できるデータプロバイダーの情報
- ブルームバーグやロイターなどの金融情報サービス
2. 単位・小数点の処理ミス
仮想通貨特有の小数点処理でのミス:
- ビットコインの単位(BTC/mBTC/Satoshi)の混同
- 小数点以下の桁数処理の誤り
- 科学的記数法(1.5e-8など)の読み間違い
- 異なる取引所での単位表示の違い
正確な処理方法:
- 保有数量は小数点以下8桁まで正確に記録
- 単価は円建てで統一して記載
- 計算結果の検算を必ず実施
- 取引所の残高証明書と照合確認
税務調査で指摘されやすいポイント
1. 評価方法の合理性
税務調査では、仮想通貨の評価方法の合理性について詳しく質問されることが多いです。
調査で確認される項目:
- 価格採用の根拠と合理性
- 複数取引所がある場合の選択理由
- 異常な価格変動時の対応方法
- 評価額算定の計算過程
対応策:
- 評価方法の選択理由を文書で説明
- 価格データの出所を明確に記録
- 計算過程をExcel等で保存
- 税理士による評価意見書の作成
2. 申告漏れの可能性
ブロックチェーンは取引記録が永続的に残るため、税務署も技術的な調査が可能です。
確認される可能性がある項目:
- ブロックチェーン上の取引履歴
- 取引所への照会による残高確認
- 相続人名義の新規口座開設状況
- 相続後の仮想通貨売却履歴
事前準備:
- すべての取引所・ウォレットの残高確認
- ブロックチェーンエクスプローラーでの取引履歴確認
- 相続人全員の保有状況の把握
- 適切な記録管理体制の構築
相続した仮想通貨の売却時における税務処理
売却時の所得税計算方法
相続により取得した仮想通貨を売却する場合の税務処理について詳しく説明します。
取得費の考え方: 相続で取得した仮想通貨の取得費は、相続税評価額となります。これは株式の相続と同様の取り扱いです。
- 取得費 = 相続税申告で計上した評価額
- 取得日 = 相続開始日
- 売却益の計算 = 売却価額 – 相続税評価額
計算例:
相続時の評価:1BTC = 4,500,000円
売却時の価格:1BTC = 5,000,000円
譲渡所得 = 5,000,000円 - 4,500,000円 = 500,000円
所得区分: 仮想通貨の売却による所得は「雑所得」に分類され、総合課税の対象となります。
- 給与所得等と合算して税率を適用
- 最高税率:所得税45% + 住民税10% = 55%
- 事業的規模の場合は事業所得の可能性もあり
損益通算と繰越控除:
- 雑所得内での損益通算は可能
- 他の所得(給与所得等)との損益通算は不可
- 損失の翌年以降への繰越控除は不可
取得費の考え方と注意点
1. 相続税評価額の適用
相続した仮想通貨の取得費は、被相続人の取得価額ではなく、相続税評価額(時価)となることが重要なポイントです。
【間違った計算】
被相続人の取得価額:1BTC = 2,000,000円
相続時評価額:1BTC = 4,500,000円
売却価額:1BTC = 5,000,000円
誤った譲渡所得 = 5,000,000円 - 2,000,000円 = 3,000,000円
【正しい計算】
相続時評価額:1BTC = 4,500,000円(取得費)
売却価額:1BTC = 5,000,000円
正しい譲渡所得 = 5,000,000円 - 4,500,000円 = 500,000円
2. 分割相続の場合の取得費
遺産分割により複数の相続人が仮想通貨を取得した場合:
- 各相続人の取得費は相続分に応じて按分
- 分割時期による価格変動は考慮しない
- 遺産分割協議書に記載された割合で按分
3. 小数点以下の処理
仮想通貨特有の小数点処理:
- 取得費も小数点以下の数量で正確に計算
- 売却時の数量と正確に対応させる
- 端数処理は一般的な商慣習に従う
確定申告での処理方法
申告書の作成方法:
- 申告書B(第二表)の雑所得欄に記載
- 所得の種類:「仮想通貨売却」
- 支払者:「取引所名」
- 収入金額:売却価額
- 必要経費:取得費(相続税評価額)
- 必要な添付書類:
- 仮想通貨売買報告書(取引所発行)
- 相続税申告書の写し(取得費証明)
- 売却時の取引履歴
記載例:
雑所得の内訳
種目・所得の生ずる場所:仮想通貨売却・コインチェック
収入金額:5,000,000円
必要経費:4,500,000円(相続税評価額)
所得金額:500,000円
注意すべきポイント:
- 売却のタイミング:相続税納付資金のための売却は早めに検討
- 税率の影響:他の所得との合算による税率アップを考慮
- 分割売却:複数回に分けて売却する場合の管理方法
- 記録の保持:売却から7年間は関連書類を保存
仮想通貨相続税対策と事前準備
生前にできる相続税対策
仮想通貨の相続税負担を軽減するための生前対策について解説します。
1. 生前贈与の活用
年間110万円の贈与税基礎控除を活用した対策:
- 毎年110万円以内の贈与:贈与税の負担なしで財産移転
- 複数年にわたる計画的贈与:大きな資産も段階的に移転可能
- 複数の相続人への分散贈与:基礎控除額を最大限活用
実務上の注意点:
- 贈与時の仮想通貨価格で贈与税を計算
- 毎年異なる日時・金額で贈与(定期贈与の否認回避)
- 贈与契約書の作成と贈与の事実を明確化
- 受贈者名義の口座で管理(名義預金の否認回避)
2. 相続時精算課税制度の利用
将来の値上がりが期待される仮想通貨に特に効果的:
- 2,500万円まで贈与税非課税
- 贈与時の価額で相続税計算
- 値上がり分の相続税負担なし
活用例:
現在価値:1BTC = 3,000,000円
10年後予想:1BTC = 10,000,000円
相続時精算課税で贈与した場合:
→ 相続税計算は3,000,000円ベース
→ 7,000,000円の値上がり分は相続税負担なし
3. 家族間での取引所分散
相続税評価の複雑化回避策:
- 被相続人の取引所アカウントを整理
- 主要取引所1-2社に集約
- 家族それぞれ異なる取引所を使用
- 評価時の価格算定を簡素化
仮想通貨の管理方法と記録保持
1. デジタル資産の一覧表作成
相続人が確実に把握できるよう、以下の情報を記録:
【記録すべき項目】
・取引所名・ログインID
・保有仮想通貨の種類と数量
・ウォレットの種類とアドレス
・秘密鍵・シードフレーズの保管場所
・2段階認証の設定方法
・緊急連絡先(取引所・税理士等)
2. セキュリティを考慮した情報管理
- 物理的保管:銀行貸金庫での重要書類保管
- 暗号化:デジタルデータの暗号化保存
- 分散保管:情報を複数箇所に分けて保管
- 定期更新:アカウント情報の変更時は速やかに更新
3. 取引履歴の保存
税務調査や評価額算定に備えた記録保持:
- 月次取引報告書のダウンロード・保存
- 重要な取引のスクリーンショット保存
- ステーキング・DeFi取引の詳細記録
- 税務計算用のExcelファイル作成
専門家への相談タイミング
1. 早期相談が推奨されるケース
以下の状況では早めの専門家相談を推奨:
- 仮想通貨の保有額が1,000万円を超える場合
- 複数の取引所・DeFiプロトコルを利用している場合
- 海外取引所でのみ取引可能な通貨を保有している場合
- マイニング事業や仮想通貨関連事業を行っている場合
- 相続財産全体の評価額が基礎控除額に近い場合
2. 相談する専門家の選び方
- 仮想通貨税務の実績豊富な税理士
- 暗号資産に関する知識・経験が十分
- 相続税申告の経験が豊富
- 国税庁の最新見解に精通
3. 相談時の準備資料
効果的な相談のために準備すべき資料:
- 全取引所の残高証明書
- 過去3年分の取引履歴
- ウォレット残高とアドレス一覧
- 家族構成と相続関係図
- 他の相続財産の概要
- 相続対策の希望・方針
相談費用の目安:
- 初回相談:1-3万円程度
- 相続税申告業務:財産規模に応じて50-200万円
- 生前対策コンサルティング:月額5-10万円程度
- 仮想通貨評価意見書作成:10-30万円程度
費用対効果を考慮し、財産規模に応じて適切な専門家サポートを受けることが重要です。
まとめ:適正申告で安心な仮想通貨相続を
仮想通貨の相続税について、国税庁の公式見解に基づく正確な知識をお伝えしました。重要なポイントを改めて整理します。
仮想通貨相続税の基本原則:
- 仮想通貨も通常の財産と同様に相続税の課税対象
- 相続開始時点での時価(市場価格)で評価
- 活発な取引所の価格を基準とした合理的な評価が必要
- 申告期限は相続開始から10か月以内
適正申告のための重要事項:
- すべての取引所・ウォレットの残高を漏れなく把握
- 信頼できる価格データを使用した正確な評価
- 必要書類の完備と計算根拠の明確化
- 複雑な場合は専門家による支援の活用
相続後の税務処理:
- 売却時は相続税評価額を取得費として所得税計算
- 雑所得として総合課税の対象
- 適切な記録保持と確定申告の実施
生前対策の重要性:
- 計画的な生前贈与による税負担軽減
- デジタル資産の適切な管理と記録保持
- 相続人への情報共有と引継ぎ準備
仮想通貨の相続は比較的新しい分野ですが、適切な知識と準備により安心して対応することができます。不明な点がある場合は、仮想通貨税務に精通した税理士に相談することをお勧めします。
また、これから仮想通貨投資を始める方や、相続対策として家族に仮想通貨を贈与したい方は、信頼できる取引所選びが重要です。コインチェックは金融庁登録済みの安心できる取引所で、相続時に必要な各種証明書の発行にも対応しています。まずはアカウント開設から始めて、適切な仮想通貨投資と相続対策を進めましょう。
適正な申告により、税務リスクを回避し、安心して仮想通貨資産を次世代に引き継ぐことができます。デジタル資産時代の相続対策として、今回の内容を参考に準備を進めてください。
\ 暗号資産の世界を一歩踏み出せ /
投資に関するおすすめの書籍
1. 『ウォール街のランダム・ウォーカー』(バートン・マルキール著)
初心者から経験者まで、投資の基礎を学ぶのに最適な一冊。分散投資やインデックス投資の重要性を詳しく解説しています。
¥2,673 (2026/01/22 22:10時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
2. 『株式投資の未来~永続する会社が本当の利益をもたらす』*(ジェレミー・シーゲル著)
長期投資の視点から、株式市場の成り立ちや成功する投資戦略を紹介しています。
¥2,420 (2024/12/22 04:41時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
3. 『金持ち父さん貧乏父さん』(ロバート・キヨサキ著)
投資やお金に関する考え方を学ぶのに最適。資産形成の基本を学びたい方におすすめです。
¥1,870 (2026/01/22 22:10時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
4. 『敗者のゲーム』(チャールズ・エリス著)
投資家が陥りがちな失敗と、その回避法を詳しく解説しています。インデックス投資を中心にした内容です。
¥2,200 (2026/01/22 22:10時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
5. 『バビロンの大富豪』(ジョージ・S・クレイソン著)
お金を増やすための古典的な原則を物語形式で紹介しています。初心者にも分かりやすい内容です。
¥1,782 (2026/01/19 21:09時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
これらの書籍を通じて、投資の知識を深め、ビットコインや他の資産への理解を広げていきましょう!





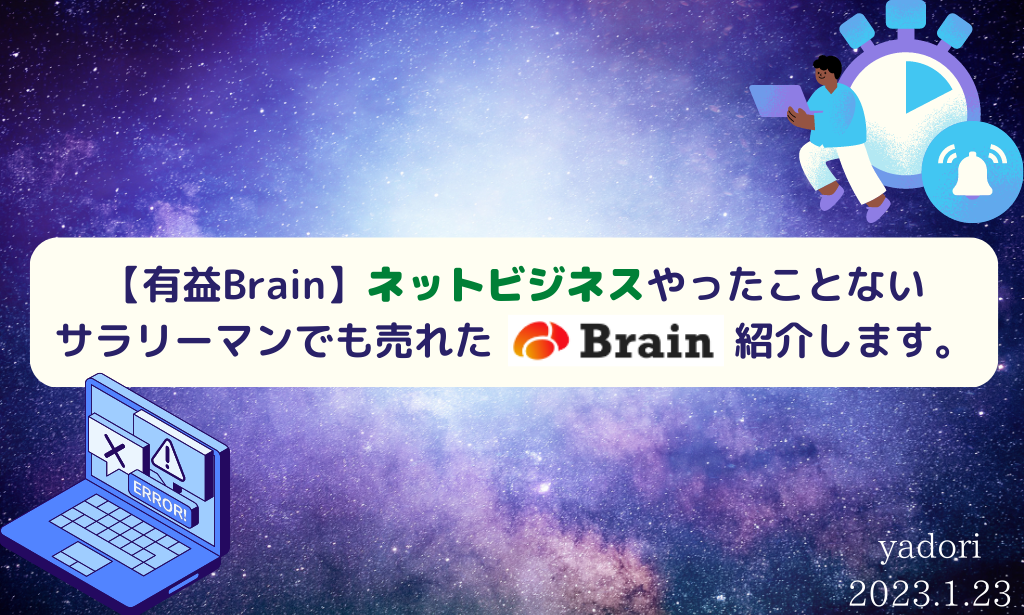






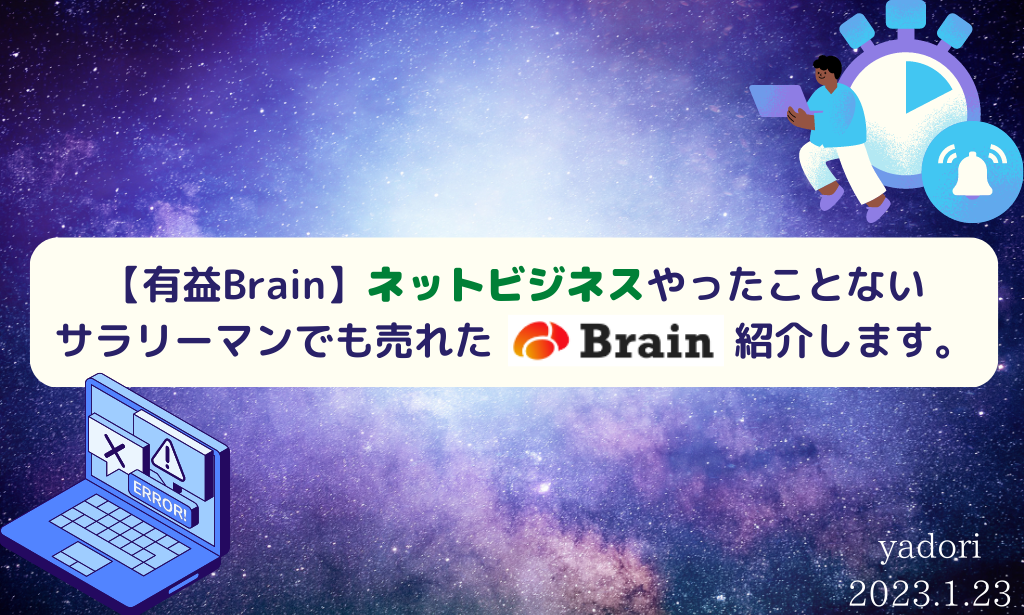









コメント