オススメの暗号資産交換所
みっんな使ってる

イーサリアムが安い

暗号資産銘柄の取り扱い数No.1

オススメのブログテーマ
早めに始めないと損

個人で稼ぎたい方へ
ブロガー必見のメルマガ紹介

アフィ成功事例
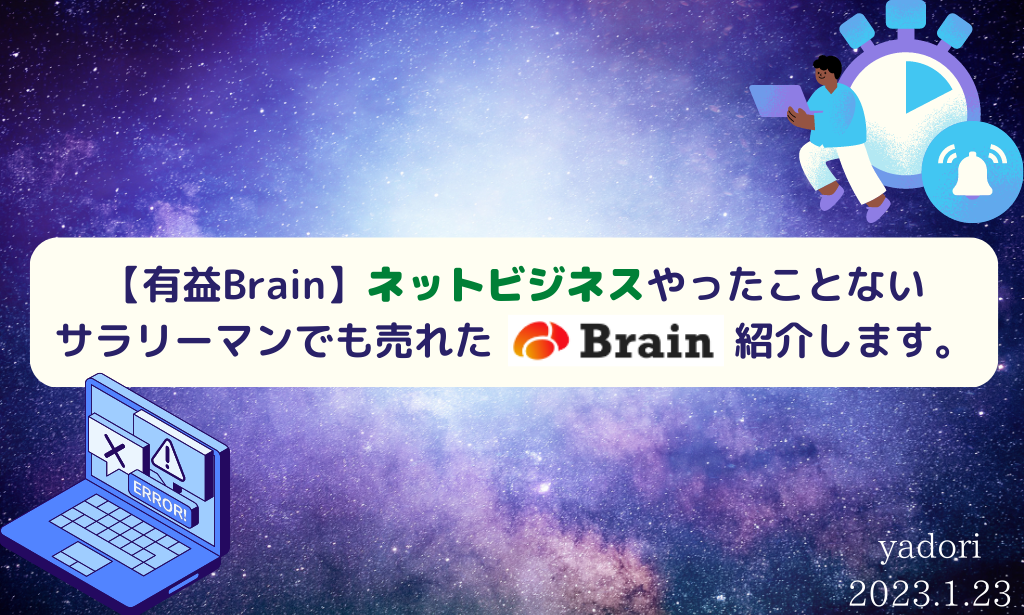
『ながら読書』最強!

みっんな使ってる

イーサリアムが安い

暗号資産銘柄の取り扱い数No.1

早めに始めないと損

ブロガー必見のメルマガ紹介

アフィ成功事例
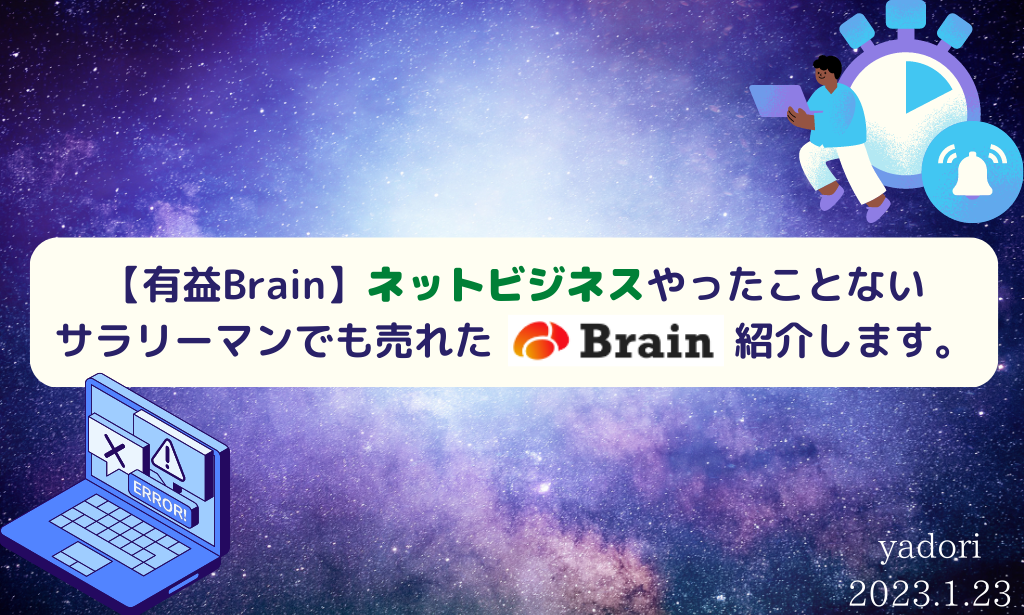
『ながら読書』最強!

ねぇ、みんな! 仮想通貨の取引で、お金が増えて「やったー!」って喜んだり、逆に減って「ガーン…」ってガッカリしたり、そんな経験、ありませんか?
ビットコインやイーサリアムみたいないろんな仮想通貨を買ったり売ったり、いくつかの取引所を使っていると、「あれ?結局、私、今年いくら儲けたんだっけ?損した分は引けるのかな?」って、頭がこんがらがっちゃうこと、ありますよね。
大丈夫!そんなあなたの悩みを解決する、魔法みたいなワザがあるんです。それが「損益通算」!
このワザを知って、ちゃんと使えば、余分な税金を払わなくて済むかもしれませんよ?
まるで、お小遣い帳をつけるみたいに、今年の仮想通貨の利益と損した分をキレイに計算して、税金を少なくする方法を、小中学生でもわかるように、じっくり教えちゃいます!
初心者さんでも大丈夫!使いやすいアプリで、人気のビットコインなどをすぐに始められます。今すぐ無料で口座を開いて、新しい世界に飛び込もう!
\ 取扱通貨数が国内最大クラス /
最近、仮想通貨の投資がすっごく人気だよね。
「ビットコインでたくさん儲かった!」と思ったら、別のアルトコインで大きな損をしちゃった…なんてこと、ありませんか?
「Aっていう取引所では利益が出たけど、Bっていう取引所では損しちゃった」なんて話もよく聞くよね。
こんな時、「今年の税金、どう計算すればいいの!?もう、どこから手をつけたらいいか分からない!」って、まるでテスト前に白紙の答案用紙を前にしたみたいに、途方に暮れちゃう人もいるはず。
大丈夫、一人で悩まないで!
一つ一つの取引を全部自分で見て、いついくらで買って、いついくらで売ったか、なんて調べるのは、宝探しゲームで手がかりが少なすぎるのと同じくらい大変なこと!
仮想通貨の税金の話って、学校では教えてくれない、ちょっと難しい専門用語がいっぱい出てくるよね。
特に「損益通算」って何?どこまで使えるの?って、誤解している人も多いんです。
「せっかく一生懸命投資したのに、損した分が税金から引いてもらえないなんて、なんか納得いかない!」
そんな気持ち、すごくよく分かります。
でも、安心してください!このページでは、そんなあなたの不安を「えいっ!」と吹き飛ばすために、税金をもっと少なくできる、特別な情報をお届けします。
正しい「損益通算」のルールを知って、使えば、必要のない税金を払うことなく、あなたの手元に残るお金を増やすことができますよ!
まるで、お小遣いを賢く貯めるみたいに、税金の知識を身につけて、自信を持って税金の手続きを終わらせましょう!もう、税務署からの電話におびえる心配もありません!
「損益通算」って言葉、聞いたことはあるけど、「それって一体、何のこと?」って思う人もいるよね。
ここでは、損益通算の基本的な意味と、仮想通貨の利益や損が「雑所得(ざつしょとく)」っていう種類になることが、なんで大事なのかを、一つずつ分かりやすく説明します。
損益通算っていうのは、たとえば今年の1月から12月までに、
**「じゃあ、足し引きして、結局いくら儲かったってことにしようか?」**って計算する仕組みのことなんです。
これは、みんなに公平に税金を払ってもらうための大事なルール。
例えば、おもちゃの売買で100円儲けたけど、カードゲームで100円損しちゃった。合計で考えれば、儲けはゼロだよね。
でも、もし損した分を引いてくれなかったら、「儲けた100円にだけ税金払ってね」って言われるようなもの。それって、ちょっと unfair(アンフェア)だよね?
損益通算は、そんな unfair をなくして、本当に儲かった分だけに税金がかかるようにするための、大切なワザなんです。
仮想通貨を売ったり買ったりして得た利益や損失は、国のルールでは「雑所得(ざつしょとく)」という種類のお金として扱われます。
この「雑所得」っていう名前が、損益通算を考える上で、とっても大切なんです!
税金の世界には、いろんな種類のお金があります。
会社からもらうお給料(給与所得)、お店をやって儲けたお金(事業所得)、アパートの家賃(不動産所得)とかね。
それぞれ、計算の仕方や税金のルールが違うんだ。そして、損益通算で足し引きできる範囲も、それぞれ決まっています。
特に「雑所得」は、他の所得と損益通算できる範囲が、ちょっと狭いんです。
だから、仮想通貨の税金を計算する時は、**「あ、これは雑所得なんだな」**ってことを、しっかり覚えておくのがポイントですよ!
「持ってるいろんな仮想通貨で、儲かったのと損したのがあるんだけど、これって、まとめて計算して税金を少なくできるの?」
仮想通貨に投資しているみんなが一番知りたいことだよね!
結論から言うと、「はい、できます!」
ここでは、その具体的なやり方と、ちょっと気をつけるポイントを教えちゃいますね。
そう!あなたが持っているたくさんの仮想通貨で、損益通算をすることができます。
たとえば、こんな感じ!
この場合、どうやって計算すると思う?
やったね!これで、最終的に税金がかかるのは「8万円」だけになりました!
もし、損益通算ができないと、利益が出た23万円全部に税金がかかっちゃうところだったから、このワザがどれだけ大切か、よく分かったかな?
「私、Aっていう取引所とBっていう取引所、両方使ってるんだけど、それでも大丈夫?」
はい、大丈夫です!複数の取引所を使っている場合でも、それぞれの取引所で出た利益と損失を全部まとめて、損益通算することができます。
例えば、こんなケースを見てみましょう。
この時の計算は、こうなります。
見てみて!いろんな取引所を使ってても、最終的に税金がかかるのは「18万円」だけになりました!
大事なのは、**「どこの取引所で取引したか」よりも、「あなたの1年間の仮想通貨の取引全部で、結局いくら儲かったか」**ってことなんです。
だから、日本国内の取引所でも、海外の取引所でも、使っているところ全部の取引をしっかり集めて、正しい儲けの合計を出してくださいね!
ここ、とっても大事な注意点です!
「FX取引」って聞くと、ドルやユーロみたいな外国のお金を売買するイメージがあるかな?
仮想通貨の「現物取引(げんぶつとりひき)」や、ちょっと複雑な「信用取引(しんようとりひき)」「先物取引(さきものとりひき)」などで出た利益や損は、ぜーんぶ「雑所得」として一緒に計算できます。
でも、外国のお金(法定通貨)を売買する「FX取引」で出た利益や損は、仮想通貨とは税金のルールが違うんです!
FX取引は「申告分離課税(しんこくぶんりかぜい)」っていう、特別なルールで税金が計算されます。
これは、「外国のお金を売買した時の儲けは、他の儲けとは混ぜないで、別々に税金を計算してね」っていう意味。
だから、仮想通貨の取引で儲けたり損したりした分と、外国のお金を売買するFX取引で儲けたり損したりした分は、一緒に「損益通算」することはできないんです。
まるで、サッカーとバスケットボールで違うルールがあるみたいに、税金の世界にも「これはこのルール、あれはあのルール」って決まりがあります。
この点を間違えないように、しっかり覚えておいてくださいね!
「仮想通貨で損しちゃった分を、お給料や、お店で儲けた分と合わせて税金を安くできるのかな?」
そう考えた人もいるかもしれませんね。
残念ながら、仮想通貨の損失(雑所得)は、他の種類のお金とは一緒に計算できる範囲が、ごく限られています。
仮想通貨の利益や損は、「総合課税の雑所得(ざつしょとく)」っていう種類のお金でしたよね。
だから、原則として、同じ「総合課税の雑所得」の仲間どうしなら、損益通算ができます。
たとえば、あなたが文章を書く副業をしていて「原稿料」をもらったり、インターネットで商品を紹介して「アフィリエイト収入」を得たりしていたとします。これらも「雑所得」の仲間なので、仮想通貨で損した分と合わせて計算して、税金を安くできる可能性があります。
ただし、ここで「お店の儲け(事業所得)」や「アパートの家賃(不動産所得)」って言葉が出てくるけど、これらは普通、「雑所得」とは別の種類のお金として扱われるんです。
ごく稀に、小さなお店や副業の規模で、継続性がないと判断された場合に「雑所得」として申告することもあるけれど、基本的には、仮想通貨の損失と、あなたのお給料や本業の事業所得を直接的に合わせて税金を安くすることはできません。
あくまで**「総合課税の雑所得」の仲間どうしでしか足し引きできない**、と覚えておくのが安心ですよ。
悲しいお知らせだけど、仮想通貨で損した分を、あなたが会社からもらっているお給料や、本業でやっているお店の儲けと合わせて税金を安くすることはできません。
なぜなら、これらのお金は、税金の世界で「種類が違う」と決められているからです。
たとえば、会社員の方が1年間で仮想通貨でたくさん損をしてしまっても、その損した分を、お給料にかかる税金から引いてもらうことはできないんです。
これは、仮想通貨の利益が「総合課税の雑所得」として扱われるという、国の税金のルールのきまりなんです。
株の投資や投資信託で儲けたり損したりしたお金、それからさっき話した外国のお金を売買するFX取引で儲けたり損したりしたお金も、仮想通貨の利益や損とは一緒に損益通算することはできません。
その理由は、これらのお金が**「申告分離課税(しんこくぶんりかぜい)」**という、別の特別な税金ルールで計算されるからです。
このように、お金の種類や税金の計算方法が違うと、損益通算は認められないんです。
仮想通貨の損失は、あくまで**「総合課税の雑所得」の範囲内でしか足し引きできない**、ということを、しっかり頭に入れておきましょう!
損益通算のルールが分かったところで、次は実際にどうやって計算するのか、具体的な例を見ていきましょう。
正しい計算は、税金の手続きをしっかり終わらせて、ちゃんと税金を払うために、とっても大切だよ!
損益通算をする上で一番大事なこと。それは、その年の1月1日から12月31日までの間にあった、仮想通貨の取引ぜんぶの**「儲け」と「損」を正確に知ること**です。
これには、こんな情報が必要になります。
これらの情報を手作業で全部集めて計算するのは、まるで夏休みの宿題を最終日にまとめてやるくらい大変!
だから、たくさんの取引をした人は、後で紹介する「損益計算ツール」を使うことを、強くおすすめします!
あなたが1年間で、こんな仮想通貨の取引をしたとします。
さあ、この時の損益通算はどうなるでしょう?
この場合、最終的に税金がかかる仮想通貨の儲けは「8万円」になります。
もし損益通算ができないと、利益が出た23万円に税金がかかっちゃうから、この計算がいかに大切か、よく分かったかな?
あなたが1年間で、いろんな取引所を使っていて、こんな儲けや損が出たとします。
この時の損益通算は、こうなります!
この例では、複数の取引所を使っていても、すべての儲けと損を足し引きして、最終的に税金がかかるのは「18万円」になります。
大事なのは、それぞれの取引所ごとに別々に計算するんじゃなくて、すべての取引をまとめて、1年間の合計の儲けを出すことですよ!
仮想通貨の儲けや損は、確定申告書Bという書類の「所得金額(しょとくきんがく)」という欄にある、「雑(その他)」って書いてある場所に書きます。
具体的なやり方は、こんな感じ。
国の税金の手続きをインターネットでできる「e-Tax(いーたっくす)」を使えば、質問に答えていくだけで、自動で正しい場所に書いてくれるから、書類を作るのがすごく楽になりますよ!
仮想通貨の損益通算は、税金を安くするのにとても役立つワザだけど、いくつか知っておくべき大切なポイントや注意点があります。
これを知らないと、「え!そんなはずじゃなかった!」って、思わぬ落とし穴にはまっちゃうかもしれません。
「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」っていう、国のインターネットサービスを使えば、お家からパソコンやスマホで、簡単に確定申告の手続きができます。
これを使うと、こんなに良いことがあります!
特に、仮想通貨みたいに新しい税金のルールについては、e-Taxが「ここはこうしてくださいね」って分かりやすく教えてくれるから、間違いを少なくするのにも、とっても役立ちますよ!
ここ、とってもとっても大事なポイントです!
株の投資やFX取引で損しちゃったお金は、特別なルールで、最大3年間、来年以降の利益と合わせて税金を安くすることができます。(これを「繰越控除(くりこしこうじょ)」って言います)
でもね、仮想通貨の利益や損は「総合課税の雑所得」っていう種類なので、この「繰り越して税金を安くする」ワザは使えないんです!
つまり、今年、仮想通貨でたくさん損しちゃったとしても、その損した分を来年以降の利益と合わせて税金を安くすることはできません。
今年の損は、今年のうちに他の雑所得と足し引きしきれなかったら、税金の世界では「なかったこと」になっちゃうんです。
このルールを知っていれば、「年末までに、利益が出てる仮想通貨を売って、損した分と合わせて税金を減らそうかな?」って、年末の投資の作戦を立てることもできますよ!
会社員の方で、仮想通貨の利益など「雑所得」の合計が、1年間で20万円以下の場合は、原則として確定申告をしなくてもいいことになっています。
でもね、これは**「確定申告がいらない」ってだけで、「税金がかからない」わけじゃない**から、気をつけてね!
住んでいる市町村に払う「住民税」の申告は必要になることがあるので、確認が必要です。
また、この「20万円ルール」は会社員の人だけのお話です。自分でビジネスをしている人(個人事業主やフリーランス)など、他に確定申告が必要な人は、儲けの金額がいくらであっても、仮想通貨の利益を全部申告する必要があります。
たとえちょっとした儲けでも、税金がかかる可能性があるってことを知って、正直に申告するように心がけましょうね!
正しい確定申告をするためには、すべての取引の記録を、ちゃんと大事にしまっておくことが、とっても大切です。
税務署は、あなたの申告が正しいか確認するために「税務調査(ぜいむちょうさ)」っていうのをすることがあります。その時、こんな書類を見せてくださいって言われるかもしれません。
これらの記録は、いざという時に「私の申告はちゃんと正しいですよ!」って証明するための、とっても大事な証拠になります。
少なくとも7年間は、大切に保管しておくことをおすすめします。
複数の取引所を使っている人は、特にすべてのデータを一か所にまとめて、いつでも見せられるように整理しておくと安心ですよ!
仮想通貨の税金については、まだ新しい分野だから、「これってどうなの?」って疑問に思うことがたくさんありますよね。
ここでは、特にみんながよく疑問に思うことを、質問と答えの形で分かりやすく説明します!
いいえ、残念ながら「含み損」は損益通算の対象にはなりません。
「含み損(ふくみぞん)」っていうのは、あなたが持っている仮想通貨が、買った時よりも今の値段が下がっている状態のことです。
この損は、実際にその仮想通貨を売ったり、他の仮想通貨と交換したりして、「損を確定させないと」税金の世界では「損」として認めてもらえないんです。
損益通算ができるのは、実際に取引が行われて、「儲け」や「損」がハッキリ決まったものだけです。
だから、含み損がある場合は、その損した分を税金計算に反映させるためには、一度売って損を確定させる必要があります。
でも、その後また値段が変わるかもしれないから、売るかどうかは、よーく考えて決めてくださいね!
はい、使えます!マイニング(仮想通貨を掘り当てること)やDeFi(新しいお金の仕組み)でもらった報酬(例えば、仮想通貨を貸して増えた分とか)も、原則として「雑所得」として扱われます。
だから、他の仮想通貨を売ったりして出た儲けや損と、一緒に損益通算することができます。
これらの報酬は、もらった時の仮想通貨の値段が、あなたの収入になります。そして、その収入を得るためにかかった費用(例えば、マイニングの電気代やパソコンの費用、DeFiの取引手数料など)は、必要経費として収入から引くことができます。
マイニングやDeFiを大きくな規模で続けていて、「これはビジネスだ!」って認められる場合は、「事業所得」になることもありますが、普通の人にとっては「雑所得」として扱われることが多いです。その場合、他の仮想通貨の売却益や売却損と合わせて、1年間の雑所得を計算することになりますよ。
はい、仮想通貨の損益計算ツールは、たくさんの取引をしている人にとって、とっても便利で、ぜひ使うことをおすすめします!
これを使うと、こんなに良いことがあります。
お金がかかるものから無料で使えるものまで、いろんなツールがあります。
あなたの取引の量や、「これだけはやってほしい」っていう希望に合わせて、ぴったりのツールを選ぶといいでしょう。
ツールを使うことで、確定申告の時の「うわー、どうしよう!」っていうストレスを減らして、もっと正確に税金を払うことができますよ!
ここまで、仮想通貨の取引で儲けたり損したりした時に使う「損益通算」について、基本的なことから、具体的な計算の仕方、そして気をつけたいことまで、じっくり説明してきました。
もう一度、大事なポイントをまとめておさらいしましょう!
これらのルールを正しく理解して使えば、いらない税金を払うことなく、あなたの手元に残るお金を一番多くすることができます。
「仮想通貨の税金って難しい…」って思うかもしれないけど、一つずつ正しい知識を身につけていけば、決して怖いものじゃありません。
安心して確定申告をして、賢く税金を払いましょうね!
もし、あなたの取引記録がすごく多くて計算が複雑で不安な場合や、DeFiやNFTみたいなちょっと特別な取引をしている場合は、税理士さんみたいな税金の専門家のお兄さんやお姉さんに相談することを、強くおすすめします!
専門家は、あなたの状況に合わせて、ぴったりのアドバイスをくれたり、確定申告の書類を作るのを手伝ってくれたりします。
お金はかかるかもしれないけど、税務署から「これ、おかしいですよ?」って言われるリスクを減らせるし、一番良い方法で税金を安くする作戦を立ててくれるから、とても良い選択肢ですよ!
初心者さんでも大丈夫!使いやすいアプリで、人気のビットコインなどをすぐに始められます。今すぐ無料で口座を開いて、新しい世界に飛び込もう!
\ 暗号資産の世界を一歩踏み出せ /
1. 『ウォール街のランダム・ウォーカー』(バートン・マルキール著)
初心者から経験者まで、投資の基礎を学ぶのに最適な一冊。分散投資やインデックス投資の重要性を詳しく解説しています。
2. 『株式投資の未来~永続する会社が本当の利益をもたらす』*(ジェレミー・シーゲル著)
長期投資の視点から、株式市場の成り立ちや成功する投資戦略を紹介しています。
3. 『金持ち父さん貧乏父さん』(ロバート・キヨサキ著)
投資やお金に関する考え方を学ぶのに最適。資産形成の基本を学びたい方におすすめです。
4. 『敗者のゲーム』(チャールズ・エリス著)
投資家が陥りがちな失敗と、その回避法を詳しく解説しています。インデックス投資を中心にした内容です。
5. 『バビロンの大富豪』(ジョージ・S・クレイソン著)
お金を増やすための古典的な原則を物語形式で紹介しています。初心者にも分かりやすい内容です。
これらの書籍を通じて、投資の知識を深め、ビットコインや他の資産への理解を広げていきましょう!








コメント